人気画像(画像付)
丸に違い鷹の... (28298 hits)
|
丸に橘 (24415 hits)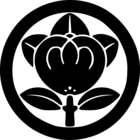
|
揚羽蝶.png (14676 hits)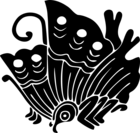
|
梅鉢 (11992 hits)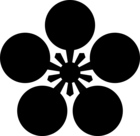
|
清和源氏諸流... (11089 hits)
|
メインメニュー
天朝を滅亡の淵から救い出した山名一族 
永徳三(1383)年二月十五日、「後愚昧記」には次のように記載されている。
「今夜、資康、仲光卿等為左府使参仙洞。而無御対面、入御御持仏堂。可被切御腹之旨、被仰之云々。是為武家。可奉配流之旨、依有荒説、如此被仰歟云々。―― 中略 ――今夜、京中下辺、依此事騒動云々。」
これは、以前から足利義満が後円融上皇を島流しにしようとしている、との巷説が流れていたので、左府(義満)の使者が仙洞御所に来た時、上皇は自分を捕らえて島流しにするために来た、との脅迫観念の為、即座に自刃せん、とされたのである。なぜなら、観応の擾乱で、光厳上皇、光明法皇、崇光天皇、東宮直仁親王が、持明院殿から南軍によって拉致され、遠く賀名生へ連行され、幽閉された。その幾星霜の艱難辛苦の言い伝えが、生々しく脳裏に蘇えったからである。
ではなぜ、上皇と義満との確執が、かくも危機的な極限状態に達したかといえば、上皇が幼い後小松天皇に譲位した時、即ち、三種の神器を受け継ぐ践祚は四月十一日に終わっていたが、即位式は後に行われるのが桓武天皇以来の通例であったので、摂政二条良基と左大臣義満が、後円融上皇に一言の相談もせず、二人で勝手に決めてしまったので、上皇の逆鱗に触れたのである。
なぜなら、上皇は治天の君であり、又、朝家の大事を家来が主人の意向も聞かずに決定するとは言語道断と激怒されたのである。結局、勅許の無いままの即位式となった。「良賢真人記」に曰く、
「(永徳二年)十二月二十八日、今日御即位也。天皇御高御座。左大臣候御帳中。為被扶持也。今日御即位事、仙洞更無御口入。摂政殿、左大臣両人被令申行之。」と。
後円融上皇の堪忍袋の緒が切れたのは、永徳三年正月二十九日の父帝である後光厳院宸忌に、廷臣達が義満の機嫌を恐れ、出仕しなかったからである。「後愚昧記」に曰く、
「二十九日、後光厳院聖忌也。然而云御八講。云御経供養。不及被行之。人々恐武家時宜、不出仕之故歟。」と。
では、なぜ公家の人々が義満の意向を恐れるのかと言えば、かつて義満が左大臣になって初めて参内する時に、廷臣はこぞって内裏の四足門に出て義満を出迎えた。ところが、気骨のある五人の朝臣は出迎えなかった。すると義満は即刻、五人の「召名」を止め、持明院基明に至っては出家遁世を余儀なくされたからである。
さて、この後円融上皇の焦眉の急を告げる事態に、前関白近衛道嗣は身を挺して北朝(持明院統)の救出に知恵を絞った。なぜなら持明院家とは藤原道長の次男頼宗の系統であり、後高倉院以降、ここは歴代の仙洞御所となった。つまり、後円融上皇も院政を行い、治天の君なのである。それが、あろうことか、義満によって滅ぼされようとしているのである。上皇が天皇の時は、関白として仕えた近衛道嗣との関係は良好であった。それは持明院家の保藤は近衛家の出自だからである。且つ、保藤の娘は内大臣洞院実夏の室であり、あの尊卑分脉を書いた洞院公定の母なのである。又、その妹は近衛道嗣の北政所であった。その上、保藤の孫、持明院保脩(やすなが)の娘は山名陸奥守氏清の正室であった。実を言えば、近衛道嗣の北政所は実夏の娘ではなく、南朝左大臣洞院実世、つまり、実夏の兄の娘であった。
わかりやすく言えば、近衛道嗣は妻を通じて南朝と連絡をとることができたのである。故に道嗣は、義満を一刻でも早く抹殺しなければならぬと考え、その誅殺役として山名氏清に白羽の矢を立てたのである。かくて南朝から「義満を誅戮すべし」との綸旨を氏清に下されるよう極秘裏に工作する一方で、持明院家を通じ、氏清に直接、北朝の院宣を伝えたのである。
南朝は真偽の程を疑い、院政を行う長慶上皇と後亀山天皇との間で、意見の一致を見るのに歳月を要した。が、ついに長慶上皇は高野山と紀伊国天野の丹生明神に、元中二(1385)年九月十日、「右、今度之雌雄、思いの如くば殊に報賽之誠を致すべし」との御願文を太上天皇寛成と自署して納められた。紀伊は氏清の兄である義理の領国であるから、山名一族への証文であろう。
氏清は南朝から、義満を討伐すべし、との綸旨を賜ったが、それよりも前に、北朝から義満を誅戮すべし、との院宣を秘密に下されていたので、即刻、挙兵すれば、本当は北朝からの命令で決起した、と義満に見破られる恐れがあったから、千載一遇の好機を待たざるをえなかった。
つまり、万一、敗戦となった時に、氏清の掲げた錦旗は北朝が授けたのだ、と義満が勘繰れば、北朝は一瞬にして滅ぼされことは火を見るよりも明らかだった。果たせるかな、ついに、その時機が到来した。
「南方紀伝下」に曰く、
「十一月、停満幸出雲守護職、罪横領仙洞御領也。満幸勧氏清企謀叛、満幸者氏清甥而又婿也。将軍赦時熈氏幸、同十日、因幡堂炎上、山名催一家参南朝、欲攻京都、南帝命春日刑部少輔顕連賜錦御旗、云々」と。
この仙洞御領横領云々は、義満が山名一族に仕掛けた陰謀だった。なるほど、出雲国横田庄は仙洞御領で間違いはないが、問題は代官の日野資教は義満の手下なのである。だから、満幸が横田庄から、資教の家人を追い出した、と訴えられたが、小守護代の村主美作守を満幸が呼び出し、尋問したところ、事実無根であることが判明した。根も葉もないことをデッチあげて、義満は一族の棟梁である氏清を挑発したのである。氏清はまさにこれを待っていたのだ。之こそ、治天の君の御宸襟を安んじ奉る千載一遇の好機ととらえた。つまり、義満が仙洞御領を口実にする限り、氏清が仙洞からの命で決起したとは義満も露ほども疑わないであろう。加之、甥にして娘婿である時煕は今、義満側にある。これは時煕が自発的に義満側に身を投じたのか、あるいは氏清の深謀遠慮なる指示によるかは不明である。しかし、これで後顧の憂いなく、近衛道嗣の伝えた院宣に応えることができる、と氏清は考えた。たとえ、山名一族が全滅しようとも、天朝の身代わりとなることができるならば、一族にとって、これほどの名誉はない。大逆罪の限りを尽くす義満のみを抹殺せんと、玉砕しようとも、悠久の大義のために乾坤一擲の戦いに臨んだのである。
ただひたすら天朝の安泰を念じて、天長地久時ありて尽きるとも、天朝だけは神の如く正義の如く、未来永劫に神国日本にしろしめられんことを祈りつつ、山名氏清は十一ケ国の義兵を率いて、大内裏の跡である内野に、巨大な毒蛇の如くとぐろを巻く義満の大軍を強襲した。時に明徳二(1391)年十二月三十日の払暁であった。
満を持して矢は放たれた。突撃は熾烈を極め、激闘につぐ激闘であり、死闘に告ぐ死闘であった。人馬いやが上にも死に重なりて血河屍山を築きつつも、いつ果てるとも見えず、氏清自ら白刃を振るって流矢を顧みず敵陣に突入した。龍攘虎搏を展開すれども、敵は天下の大兵、ついに衆寡敵せず、山名の義軍は一敗地に塗れたのである。嗚呼、忠臣氏清の身は散華すれども、魂魄はとこしえなえに、称えられ崇められるであろう。そう戒名に表現されている、氏清の戒名は宗鑑寺殿古鑑衡公大居士。
この意味は、全ての人の鑑(手本)であり、古来より今日まで、いかなる鑑[手本]となる偉人が居たとしても、氏清より偉大なる人物は居ない。なぜなら、有史以来初めて天皇家を救ったのだから、という含意である。おそらく、天朝の側近から賜ったのであろう。およそ、戒名に同じ漢字を二度も使うことは無いからである。
氏清の辞世の句は、
取りえずば消えぬと思へ梓弓 引きて帰らぬ道芝の露
(この取るは天下をでは無く、義満の首級を、である)
御台(左近衛中将・持明院保脩女)の辞世、
沈むとも同じく越む、待てしばし 苦しき海の夢の浮橋
氏清の正室のこの覚悟を読むと、北朝の密勅、即ち、大逆罪を犯す義満の首級をあげよ、という院宣は近衛道嗣から御台を通して氏清に伝えられたのであろう。近衛道嗣は尊卑分脉によれば、至徳四(1387)年三月十七日に薨去している。つまり、氏清陣没の三年前であるが、およらく死の直前まで氏清に決起を促し続けたのであろう。氏清の討ち死に後、御台は湯水を断って、この二首の辞世を胸の上で組んだ手に握り締め、明徳三年正月十三日の暮れほどに、ついにむなしく亡くなった。
さて、その後の義満の悪逆の振る舞いを見ていくと、まず、南北朝の合一に乗り出した。
南朝が存在すると、義満を朝敵として錦の御旗が下されるからである。四か条の講和条件を提示し三種の神器を北朝に帰座させたが、何一つとして実行しなかった。完全に詐欺であった。南朝に与えると約束した全国の国衙領はほとんど無きに等しかった。ましてや、両統迭立の如きは実施するつもりは毛頭なかった。
ともあれ、明徳三年閏十月五日、神器は土御門東洞院の皇居の内侍所に鎮座し、五十六年ぶりに皇統は帰一したが、治天の君である後円融上皇の懊悩は増すばかりであった。なぜなら、義満の僭上と独裁は増大し、皇統が断絶させられるか、皇位が簒奪されるのではないかと煩悶されたからである。
治天の君は蒲柳の質ではないが繊細であるが故に、何事にも鋭敏であらせられた。故に皇家が、前代未聞、空前絶後、天地開闢以来初めて、絶体絶命の窮地に陥ったことを肌で感じ取られたのである。つまり、後鳥羽上皇や後醍醐天皇は北条幕府によって島流しにされたけれども、北条氏は天皇家を廃絶しようとは露ほども考えなかったのである。誰もそれは思いもしないことであった。人は、弓削の道鏡がいたではないか、と反論するかもしれないが、道鏡は天智天皇の孫である。
故に、日本史上、初めて天皇家の絶滅を虎視眈々と狙っていたのは義満のみであった。それを直感され、絶望の極、南北朝合体から僅か六ヵ月後に後円融上皇は登霞された。時に明徳四(1393)年四月二十六日であり、まだ三十四歳の若さであった。洞院公定も上皇の後を追うかのように薨去している。その著書である尊卑分脉の中で、氏清の上に註して、「南帝の勅命を蒙むるの由、自称」と書いたのは、北朝からの勅命では決して無い、と義満が後円融上皇への猜疑心を起こすことのないように配慮したのであろう。
さて、治天の君である後円融上皇が登霞されると、義満は上皇が恐れられていた通りの悪鬼の如き本性を剥き出しにし始めた。既に永徳三(1383)年六月二十六日、義満は摂政でもなく関白でもなく、いわんや帝の外祖父でもないのに、左大臣の身で、しかも武家でありながら准三后の宣下を受け、宮廷の実権を手中に収めていたので、単刀直入にいえば、皇位簒奪の挙に出たのである。
つまり、国際的に日本国王と認知されれば、簒奪の正当性の証左となる、と義満は考えたのである。目的遂行の為に義満が打った悪逆の策は、明の皇帝に上表文を奉ることであった。
応永四(1397)年、義満は明に使いを送り、
「日本准三后源道義、書を大明皇帝陛下に上(たてまつ)る。」と書いた。
二代皇帝建文帝の返詔には、
「茲(ここ)に爾(なんじ)日本国王源道義、云々」という文言が入っていた。
これでも義満は満足せず、応永十(1403)年二月付の永楽帝への上表文で、
「日本国王臣源表す。臣聞く、云々」で始め、署名も亦、「日本国王臣源」であった。
臣の字を何度も使ったのは、明の皇帝には臣事するが、日本の天皇には臣従しない、という決意が透けて見える。
次いで、諒闇(りょうあん)にかこつけて、義満は後小松帝一代の治世に二度の諒闇は不吉であると、言い募り、応永十三(1406)年十二月二十七日、義満の正室である日野康子を准母とする勅書を出さしめた。
諒闇とは天皇の父母の死に際し、喪に服すことであるが、一代で二度の諒闇は、もともと奇瑞だとされていた。しかるに義満は凶兆だと主張し、国母である藤原(三条)厳子は死んだが、准母を置くことによって、凶を吉に転換できるとしたのである。しかし、これこそ天皇家にとって、最悪の極限状態に突入することになった。つまり、これで義満は准父(准国父)、即ち、天皇の父に准じ、准上皇ということになるのである。
かくて、風雲急を告げて、地上の悪鬼は天界の神に挑みかかった。翌年の応永十五(1408)年は、天皇家にとって空前絶後の危急存亡の秋となり、まさに風前の灯であった。
二月二十七日、義満の次男義嗣が未だ十四歳で元服前だというのに参内したのである。これは義満を上皇と見立てて、その皇位継承者に擬せられたのである。続いて三月八日から二十八日まで、後小松天皇に義満の北山第への行幸を仰ぎ、というよりは強制し、もう一度公卿全員に念を押すかのように、義満は天皇と同じ繧繝縁(うんげんべり)の畳に座ったのである。この繧繝縁の畳とは玉座のことで、天皇又は上皇以外、何人といえども用うべからざるものなのである。つまり、義満は朝廷の全員に、自分は上皇である、と宣言したのと同然であった。
かくて、四月の二十五日、義満は最後の仕上げ、というより天上界の破壊を始めたのである。即ち、義嗣が内裏で元服するという、破天荒な極悪非道の暴挙に出たのである。今や義満は仮面をかなぐり捨て、悪魔の正体、いや、魑魅魍魎の如き妖怪の姿を現したのである。伏見宮貞成親王の「椿葉記」に曰く、
「その四月に内裏にて元服して義嗣と名のらる。親王御元服の准拠なる由、聞こえし」と。
ここで、魔王が一撃を加えれば、即ち、後小松帝に禅譲を強要し、義嗣親王が即位すれば、天照大神の皇統は絶えてしまう。まさに断末魔の苦しみ、万事休す、という危機一髪のところで、大神は挑みかかった悪竜を電光石火、黒雲を突き破る稲光のごとく一瞬にして誅戮されたのであった。
即ち、義嗣が親王になった三日後、天佑神助があって、義満は死の床に伏す、という奇跡が起きたのである。かくて、目出度く朝家は暗黒の闇に、天照大神の燦然たる日輪を仰ぎ見ることができた。これを天の配剤と言わずして、何というべきか。兵書に曰く、
「己の徳を修めずして他人(ひと)より勝んとすれば、天、その魂を奪う」と。孟子の言にも、「力を以て仁を仮るは覇者たり。徳を以て仁を行うは王者たり」と、ある。義満には徳が無かったのである。難しく言えば、「天のなせる災いは、なお避けるべし、自らなせる災いは逃(のが)るべからず」と「書経」にある。
しかし、神の怒りでないのならば、義満は毒殺されたことになる。ある人は毒を盛ったのは世阿弥であると言う。義満の子息である六代将軍義教が「故なくして世阿弥を佐渡島へ島流しにしたからだ」、と言うのである。もし、世阿弥が犯人ならば、世阿弥に指示したのは、応永十五年四月二十日に関白を辞した一条経嗣かもしれない。彼は二条良基の子で、一条家へ養子に入ったのである。その日記「荒暦」に、
「かくの如き大儀、勅問に及ばず群議に決せず、左右(そう)なく治定云々」と、
義満が天皇家の一大事を独断で決定したことに悲憤慷慨していたからである。
しかし、世阿弥は一服盛ったかもしれないが、証拠は無い。そんな根拠の無いことよりも、ここに、重要な文面の四代将軍義持の御判御教書がある。発行されたのは、義満死後一年四ヵ月後のことである。曰く、
在[義持]御判 「丹波国宮田荘事、為大和国宇陀郡之替、且所宛行山名左近大夫将監入道調心也。然者早守先例、可致其沙汰之状如件。 応永十六年九月五日」。
これが重要なのは四代将軍義持の判が押してあることである。義持は父義満が朝廷を乗っ取ることに怖気をふるっていた。おそらく、平重盛が父清盛に諫言したように、血涙を絞って反対したのであろう、その結果、義持は激怒した義満から厳しく責勘された。廃嫡寸前であった。
ここに、重要人物が三人居る。一人は四代将軍義持。彼は義嗣が天皇になると、その前に平伏せざるを得ず、それは兄として耐えられなかった。義嗣の内裏元服にしても、外回りの警護ばかりで、父や二十歳も離れた弟を相当恨んでいた。特に弟の義嗣への憎悪は凄まじく、義満が死ぬと義嗣は逃亡したが、義持は草の根を分けても捜し出せと厳命し、怒髪天を衝く如く、10年間も探索の手を緩めず、ついに九州まで追詰めて惨殺した。
二人目は、応永十五年四月二十日から応永十六年二月二十一日まで関白であった近衛忠嗣で近衛道嗣の孫である。藤原氏の氏の長者であった。関白近衛忠嗣は義満を抹殺せよとの密命を、家訓の如く受け継いで、不惜身命の覚悟で義満を誅殺すべく尽瘁した。近衛忠嗣は初め、良嗣と名乗っていたが、忠嗣と改名したのは天子に対する忠義と、義満抹殺への不退転の決意表明である。義満暗殺の暁には、丹波国の近衛家領である宮田荘を恩賞として与えると山名左近大夫将監に密約したのであろう。この宮田荘は忠仁公(清和天皇の外祖父・藤原良房)以来、特別に相伝してきた由緒ある荘園であった。いわば近衛家の家宝を山名氏に贈与したのは、近衛忠嗣の赤誠の表れであり、命令を実行した褒美であろう。ただ、不思議なことに、この宛行状は近衛家が所蔵し、今も尚、陽明文庫の中に現存することである。
そして、最後に山名左近大夫将監入道調心(宮田時清)は、山名陸奥守氏清の決別の言の葉「生き延びて本懐を遂ぐるべし」という遺命をまっとうせんものと、千載一遇の好機を窺っていた。ここに三者は暗黙の了解で、人知れず便宜を図り、左近大夫将監が遺恨十六年、磨きに磨いた一剣を義満の上に振り下ろしたのである。義満は応永十五年四月二十八日、死の床に就き、五月六日の酉(とり)の刻(午後6時頃)事切れた。
しかしながら、義満の戒名は相国寺の過去帳には、「鹿苑太上天皇」とあり、同寺の「塔頭末派略記」には「玉竜庵は、嘉慶年中鹿苑上皇草創」と記し、また、臨川寺の位牌には、「鹿苑院太上法皇」とあり、鹿苑寺(金閣寺)の延宝六年造立の義満木像の銘には「近造刻鹿苑天皇尊像」とあるのである。ただ、先年、義満の墓である鹿苑院が同志社大学の構内から出土したのは、真に神の摂理というべきであろう。
ところで、時熈公に付いて一言触れれば、義満側に付かれたのは、氏清の指示か、又は、阿吽の呼吸で一族を分けて、戦の庭に臨むのは、保元・平治の乱以降、清和源氏の常套手段であったからである。氏清陣没の僅か一年後に氏清の菩提寺・宗鑑寺を創建されたのが、その証左である。ちなみに時熈公の正室は氏清の娘で安清無染という。
結句、左近大夫将監が拝領した宮田荘の宛行状には四代将軍義持の判が押してはあるが、本当は幕府の重鎮であった時熈公から与えられたのではなかろうか、と私は推測している。
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | 山名会/刊行物等/山名第6号/天朝を滅亡の淵から救い出した山名一族 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | admin |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | なし |
| ユーザー : | なし |
