人気画像(画像付)
丸に違い鷹の... (28297 hits)
|
丸に橘 (24414 hits)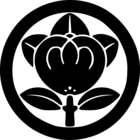
|
揚羽蝶.png (14675 hits)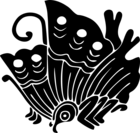
|
梅鉢 (11991 hits)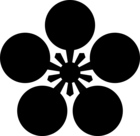
|
清和源氏諸流... (11088 hits)
|
メインメニュー
梅津長福寺 
文明五年(一四七三)三月 。 洛西梅津(現、京都市右京区梅津中村町)に甍(いらか)も高くそびえる花園上皇御願寺の大梅山長福禅寺は朝から重々しい空気に包まれています。
客殿奥の一室に臥せった西軍の総帥山名宗全が今しも七十年の生涯を閉じようとしているからです。
洛中洛外からの伝騎はいつもの通りあとを絶ちませんが、いずれも門前の衛士(えじ)に押しとどめられて、乗馬を一町(一〇九m)ほど離れた松林に繋ぎ、 足音をひそめて大方丈(本坊)に置かれた本陣へ向かうのでした。
山内の正法・大慈・瑞光ら子院に分宿している西軍方の大小名も等しく客殿の物音に耳をそばだてております。
応仁・文明の乱が勃発以来七年、山名軍は花の御所(将軍の御所)西隣の山名邸を本陣としたので、そこを西陣と言い、軍勢を西軍と呼びます。 従う武士は十数万、全国から馳せ参じた強武者揃いです。対する東軍は細川勝元を中心にこれまた十余万、合わせて三十万もの軍兵 がなだれこんでの攻め合いですから、花の都はたちまちに焼野が原となってしまいました。
『汝や知る、都は野辺の夕雲雀(ゆうひばり)、あがるを見ても、落つる涙は』 飯尾(いいのお)某はこう詠んで都の人々の悲しみのほどを訴えております。
そのころになると宗全は西軍の本陣をこの長福寺に移しています。 ここは都の西玄関です。山陰山陽を地盤とする宗全は、かねて戦術上の重要性からこの大寺に目を着け、洛東南禅寺とともに山名氏の拠りどころとしていたからです。
居室の正面押板(床の間)には宋元舶載の古筆と思しい禅画の三幅対(さんふくつい・三本で一組になった軸物)が掛けられ、その前に置かれた三具足 (香炉・燭台・花瓶)からは蘭麝(らんじゃ・銘香)の煙がうっすらと流れています。
この頃から流行しはじめた東山文化の典型的な様式です。普通なら、このような場合は正面に阿弥陀如来像を祭り、その御手から五色の綱を垂らせて病者に握らせます。仏のお迎えを信じ極楽往生を確かなものとする臨終行儀なのです。
宗全は『わしは鞍馬山の毘沙門天じゃそうな。一休坊主がそう言いよった。毘沙門天ならわざわざの来迎もいるまいよ』と笑いとぱしたということです。
しかし、かっては赤入道と渾名されるほど活力にみちた宗全の双頬は血の気を失っていました。
枕頭には禅の師であり善き友でもある南禅寺真乗院主の香林宗筒禅師(こうりんそうかんぜんじ・一説には大蔭宗松とも)や嫡孫政豊ほか身内の数人が沈痛な面持で宗全の顔を見守っています。
「・・・・ムムウッ・・・・何処じゃな、ここは。ゆゆしげな武者どらが居並んでおじやるがーー。オオッ、教豊(宗全の嫡男)ではないか、末座に控えたあの若者は・・・・。しきりに手招きをしておるわ。なるほど、あれの上座に空いた円座がひとつ。あそこがわしの席というわけか」
「・・・・ああ、父上(時熈)もおいでじゃ。祖父上(時義)も曽祖父(時氏)も・・・・。正面におわすは太祖義範公か。すると此処は上野国山名館でもあろうか。 わしはとうとうあの地を踏むことなしに終わるかと思うておったが・・・・」
「侍て教豊、じきにまいる。まいるが、その前にひとつしておかねばならぬことがある。政豊じゃ。政豊に氏の長者(棟梁・総領)の心構えを申し聞かさねばならぬ」
宗全は次第に深い水底にでも引きこまれるような眠たさと脱力感を払いのけるようにカッと両眼を大きく見開いて
「政豊ッ、政豊はおるか」 と、声だけは普段とかわりなく呼びかけました。
「ハイッ。政豊はこれに」
「うん、そうじやったな、政豊。祖父はな、今から教豊のとこへ参る。そなたの父じゃ。あれがしきりに呼んどるでな・・・・。ところで政豊、そなた幾才になりやったな」
「ハイッ、三十才になりまする」
「そうそう、そうであったわ。応仁元年の軍で教豊が矢傷を負い、それがもとで身罷(みまか)ったとき、そなたは確かニ十四じゃった。あれから六年、そなたの棟梁ぶりはよぅ身についてきた・・・・」
政豊の顔を見つめる宗全の瞼が次第に細まっていきます。
「じやがな、政豊よ。武者は強いばかりでは駄目なのじゃ。若いそなたには納得いくまいが、祖父の言い遺(のこ)しじや。よく聞いておいてくれい」 宗全はそこで話をとめて、二度三度と大きな息を継ぎました。
山名氏の台頭 
「わが家のナァ、昔のことはさて措くとして、天が下に山名ありと知られるようになったのは、そちも知っての通り中興時氏公からじゃ。公はわしの曽祖父になる。そなたには五代まえの大祖父(おおじ い)じゃな」
建武の中興 
「その頃、天下はニつに分かれていたそうな。帝や公家衆もニつ、武家もニつにじや。我等源氏のー統は執権(鎌倉幕府の最高権力者)北条氏の専横(せんおう)に堪えること百余年、いや我等ばかりではない。
時代とともに力を蓄えはじめた新興武豪集団。これらも幕府の体制からはみ出した冷や飯組じゃ。
時あたかも皇位を嗣がれた後醍醐の帝は御名の通り醍醐・村上天皇の御代・―延喜天暦(八九七ー九五六)の昔を回復し、天下の権を幕府から取り戻さんがために、討幕の綸旨(りんじ)を諸方に降されたのじゃ。
なかでも、新田・足利という源家の名門には大きな期待がかけられていたぞ。
元弘三年(一三三三)、足利氏は都の六波羅(幕府軍の京都駐屯本部)を陥し、新田氏は鎌倉を降して、執権高時を自滅に追いこんだわ」
「わが祖時氏公は新田氏の流れながら、足利方に与された。これは賢明な選択であった。尊氏公とは従兄弟半という血縁もさることながら、新田の棟梁義貞公と尊氏公の人物の軽重を見抜かれてのことぞ」
「こうして出来上がった蓮武の中興も、平安王朝の栄華到来とばかり有卦(うけ)に入る貴族連と、一所懸命―おのがかち得た土地を命がけで守る―を旨とする武士層は所詮共存することができなんだ」
「こんな戯れ歌が流行したと言うぞ。
このごろ都にはやるもの 夜討・強盗・謀綸旨(にせれんじ)……
着つけぬ冠上の衣(きぬ) 持ちもならわぬ笏(しゃく)持ちて 内裏(だいり)まじりは 珍らしや…
義貞公は新政権に加わって、一時は威勢を振ったかに見えたが、それも僅か三年たらず、新政に抗する武士団に追われて越前の国で敗死、帝は吉野の山中に亡命されるというあっけない結末じゃ。
片や尊氏公は武家・農民層の保護者として、推されて室町幕府を開かれたわい。 わが時氏公は、時代がこのように動くのをお見通しだったのじゃ」
観応の擾乱(じょうらん) 
「ところがじや。公平で私欲のうすいが評判の尊氏公にも敵が出てきてのぅ。
腹心の執事高師直(こうのもろなお)をまず失い、それが片付いたかと思うと実の弟直義(ただよし)公と不和がおきる。
帝もまた京と吉野の両方で、それぞれ己こそ正統と張り合うてござる。
天下はまたしてもニつに割れてしもうたわい。
時氏公は思われるところあって、一時(いつとき)吉野の南朝から錦旗をいただかれてのぅ。十二年が程、西国の諸所で武名を挙げられた―。伯誉・因幡・但馬・美作…・・」
「……こう言えば軍好きの猪武者とも思えようが、違うのじゃ。政豊よ。曽祖父(ひいじい)はな、攻めるときには火を吹くばかりに攻め、和するときは親子兄弟にも勝るほどの睦まれようであったそうな。
われらが本貫とする但馬の国がそれじや。
この国には飛鳥・奈良の昔から勢力を張ってきた豪族がおってのう。今の太田垣・垣屋・八木らがそれじゃ。
曽祖父は彼等と戦うて但馬の国を攻め取るよりも、笑顔のうちに味方に引き入れる方が良策と、まああれこれ苦労はあったものの、今では山名四天王ということでわが家の重臣に納まっておるわい」
六分一殿 
時氏(一三〇三~一三七一)は世に「六分一殿」と呼ばれています。
一族で日本六十余か国の六分のー(伯耆・因幡・美作・但馬・丹波・丹後・紀伊・和泉・備後・出雲・隠岐の十一か国)を領するという足利幕府きっての大勢力を備えたからです。
時氏には十七男五女という沢山な子がありました。なかでも師義(もろよし)・義理(よしまさ)・氏冬・氏清・時義等が知られています。
明徳の乱 
坂東の一荘に興った山名氏がここまで急成長した事実は、山名一族にとって喜んで良いのかどうか。
時氏・時義というニ大実力者が世を去ったころ、三代将軍義満は”山名つぶし”にとりかかりました。
山名氏の総領時熈(ときひろ・時義の嫡子)とその伯父氏清・義理らの間に楔を打ちこんで内部分裂を計ったのです。
将軍は初めに氏清を使嗾(しそう)して時熈を除こうとし、翌年には時熈側の後押しをして氏清等を叛乱させる―。
これを”明徳の乱”といいます。
この戦には将軍みずからも幕府軍を率いて出陣しましたから、氏清等は逆賊の汚名をかぶらねばなりませんでした。
悲憤に燃えた氏清軍は自滅を覚悟で奮戦、武門の意地を示して討死します。
時に明徳二年十二月三十日、氏清四十八才、時熈二十五才でした。
戦後五日目の明徳三年一月四日には早くも山名一族の所領が没収・再配分されました。
総領家時熈には但馬・因幡・伯耆の三国が辛うじて認められたのです。
北野経王堂 
余談ですが、将軍義満はこの氏情討伐が余程気になったとみえ、氏清戦死の地に一大堂を建てて鎮魂の供養をしています。
これが北野の経王堂です(現、右京区千本釈迦堂あたり)。
経王とは法華経のことで、追善供養にはこの経を読むことが最高とされます。 将軍は毎年期日を定めて万部経会をつとめました。 法華経はー部八巻二十八品(章)という長編ですから、僧侶一人につきー部の割で、万部では延べー万人となります。
記録によると、毎年十月五日から十四日までの十日間、毎日千人もの僧侶が出仕しています。初日には歴代の将軍や御台所(奥方)が参詣聴聞する仕来(しきた)りです。
これだけの大法要を恒例としたのですから、義満将軍の心底がわかろうというものです。
再中興宗全 
長広舌がこたえたのでしよつか、宗全は目を閉じて呼吸を調えていましたが、うっすら瞼を開けて話を続けました。
先ほどより声の調子が低くなっております。
「政豊よ。今ひとつ申しておかねばならぬ。聞こえるか」
「ハイツ、よく聞こえまする」
「そうか、では言おう。ほかではない、播州(現、兵庫県域の南半分)のことじゃ。あそこを手にいれたのはこの祖父の仕事―。そなたも知っていようが」
「ハイ、だいたいは聞いておりまする」
嘉吉の変 
「あれは嘉吉(かきつ)一九年(一四四一)。そなたの生まれる三年前だったか。お隣の赤松がどえらいことをやりよってのう。公方(六代将軍義教・よしのり)は首を落されるし、我等が家の子熈貴(氏冬系、因幡守護職)も巻きぞえを喰ろて斬り殺される―。 赤松には赤松なりの理由があってのことじゃろが、反逆は反逆。
追討の鰯手を仰せつかったからには是が非でも我が手で赤松を攻め亡ぼさねばと、二万五千の兵を二手に分けて播州へなだれこんだな。
満祐(みつすけ・赤松総領家)は覚悟を決めていたとみえ、城の山(きのやま)城に楯館(たてこも)りはしたが、思いのほかあっけなく自裁(自決)しよった。 我が家はその功で播磨・備前・美作などをたまわり、ようやく家運を挽回しおおせたが―・・」
「さて、この播磨が難物じゃ。知っての通り公方(八代将軍義政)は、おのが父を殺した赤松の罪を許すのみか、我等が血を流して得た播備作の権益を、こともあろうに赤松の若僧に呉れてやるなど、正気の沙汰とは思われん。
またぞろ 〃山名つぶし〃 が始まったわけよ。政豊、播州は今なお山名・赤松の二派にわかれて一向に埒があかんが、この始末はそなたの仕事ぞ。 頼んだぞよ」
「ハイツ、この政豊しかと肝に銘じまして」
「じやがな、政豊。腹立ちまぎれに無理押しはするなよ。立腹すると目先がくらむわい。
そなたはまだ三十、血の気が多いのは止むを得んが、幅広く世間を見渡さねばのう。
播州のことでも赤松を見るだけではなく、公方や管領の思惑を推しはかり、挙足(あげあし)を取られぬようにすること。
それから、浦上(うらがみ・赤松幕下の実力者)ら国人衆の動きや民百姓の声にも気を配れよ。
その上に忘れてならぬことは自分の足元に注意することぞ。
祖父の代までは何とか纏めてきたが、但馬の国人衆じゃとて油断は禁物、今日の味方がいつ寝返るかわからぬのが此の世の中と
思え。それが 〃時を知る〃というものじゃ」
「ハハアーツ」
例と時 
「そうそう、時を知るといえばこんなことがあったわ。
文正二年(応仁元年)だったか、関白殿(一条兼良)がわれら武士どもの振舞を、古今にかかる無体な例はござらぬとひどう立腹(りゅうふく)されてのう。 わしはこう申しあげたわい。
『堂上方(どうじょうがた)は何かというと有職故実(ゆいそくこじつ)じゃ先例じゃと昔話をなさるが、今の世は下剋上の嵐が吹き荒れておりまする。
下下(げげ)の者と軽うみられた百姓や町人どもが一揆徒党を組んでは富豪を襲い、守護や幕府に刃向こうては徳政を要求する始末ですぞ。
この時の勢いを見落して先例にばかりこだわっていては結極時代からとり残されましょう。
今後は例ということばを時と仰せられませい』とな」
応仁の乱 
「ところがじや。えらそうにそう広言吐いたわしが時を見そこのうてしもた。
それが此度(こたび)の戦よ。
事の起りは管領家の畠山が二派に分かれての跡とり争い、どこの家でもよくあるわな。
それが、片や細川に応援を頼み、片やこの祖父に泣きついてきよった。
勝元(細川氏の総領)は娘婿ではあるし、わが子豊久(宗全の七男)を養子につかわすなど、いわば親子同然の仲じゃから、話せばわかる、そのうちに収まるわいと気軽に思うておったが、これは大きな油断であった。
宗全一世一代の大失敗よ。 勝元めはおのが領国から次々と大軍を呼び寄せてきよる。
我等も自然但馬や山陰のものどもを呼ばねばならん。火の手はあがるばかりじゃ」
「そうなると、武者どもは武者どもの立場を主張しよって、こちらの制止も何のその…―」
「公方も公方じゃ。今の公方(八代義政)には跡をとる男の子がないゆえに、舎弟の今出川殿(義視・よしみ)を次の将軍にと決めたはよいが、皮肉なことに、そこへひよっこり男の子が生まれてきよった。
それも御台所富子の方からよ。御台としてはこの子(義尚)に九代を嗣がせたい。母親なれば無理からぬ話じや。
わしも仲にはいって随分骨を折ってみたが、動けば動くほど騒ぎが大きゆうなりおって……。
肝心の公方ときたら、そんな喧嘩は御免とばかり、わびじゃ・さびじゃ・猿楽じゃ・と遊びごとに呆(ほう)けてござる。
そうなると、東軍じゃ西軍じゃという戦いももはや山名・細川の手から離れ、国をあげての新旧勢力の衝突になっ てしもうた。
まっこと時の為す業とは恐ろしいものよのう――」
「…思えばこれも、わしと勝元の不心得が引きおこしたこと―去年のはじめ、どうやら和談成立とまで漕ぎつけたが、そなたも知っての通り、赤松(総領政則)がえろう反対しおって…・―。 折角回復した播備作のうま味を失うまいとな」
「あとは言うまでもないことながら、和議失敗の責(せめ)を負うて勝元が髪を切った。
わしは切ろうにも髪がないでのう。せめてものことに雛腹(しわばら・年寄の切腹)つかまつろうと……。
そしたら皆が寄ってたかって刀をとりあげたもんじゃから、フフフ…―・・。あげくの果がこのざまよ。
政豊、潮時をみて、この騒動を収めてくれい。 わしが死んだとなると勝元も否(いな)やはあるまいよ」
宗全の臨終 
「・・・ようしゃべった。これで七十年たまった胸のつかえがおりたような…。
孫よ、障子を開けてくれい。―ーさくらが見たい―」
政豊がにじり寄って開けた障子の外には午後の春陽がやわらかく降りそそいでいました。
庭の手前の心字池には幾ひらかの花びらが浮かんでいます。
青味を増してきた築山の叡山苔にも螺鈿(らでん)を散りばめたように落花が光っています。
錆色(さびいろ)の練塀越しに姿をのぞかせる数株の老桜は、時に吹くそよ風に幾許かの花片を托して禅苑を荘厳するのです。
「政豊、起こしてくれい。最後の頼みじゃ」
肩の肉が薄くなった宗全の背を、がっしりとした若い胸に抱きながら政豊は必至のおももちで込みあげてくる嶋咽をこらえています。 と、そのとき小さなつむじ風がおこりました。
それを待ちかねていたかのように、枝という枝は一斉にそよいで、花・花・花の花吹雪を宗全に贈ったのでした。
「…はなが・・」 「・・・ちるわい・・」 これが不世出の巨人として慕われ、恐れられもした宗全の遺偈(ゆいげ)です。
文明五年三月十九日(新暦では四月中旬)没。世寿七十才。
遠碧院殿徒三位八州大守最高宗峰大居士。
遺骸は香林老師によって、長福寺境内の楠の根方で茶毘(火葬)に付され、遺骨は東山南禅寺真乗院の隠寮(いんりょう)・遠碧軒(おんぺきけん)に収められました。
同年五月、細川勝元も病没。申し合わせたような両雄の死は、世の人々に言い知れぬ感動を与えました。
翌六年(一四七四)四月三日、東西の若い総帥(そうすい)細川政元と山名政豊の間に和議が成立、傘下の諸将も相ついで領国に引きあげます。
文明九年畠山義就の帰国を最後に、十一か年に亘る大乱は終結したのでした。
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | 山名会/刊行物等/山名氏八百年/室町山名氏 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページ作成 : | admin |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | なし |
| ユーザー : | なし |
